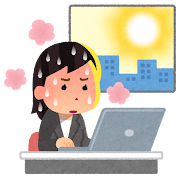
はーい。こんにちわー。
元気堂です。
夏は、とにかく汗をかき身体の中の水分が不足しがち・・・。
甘く見ていると、熱中症の危険性も出てきますね。
そんな状況に陥る前に、服用したい漢方薬に、清暑益気湯(せいしょえっきとう)があります。
これは、生脈散+補中益気湯で構成されたような漢方薬です。
まず生脈散は、汗によりナトリウム等の電解質が排出して起こる脱水症状を予防してくれます。
これは、含まれる五味子の収れん作用で過度に漏れ出るのを防ぎ、麦門冬により身体に潤いを与えます。
そして、人参で消耗した気力を立て直してくれます。
生脈散は、800年ほど前に出版された中国の書物(内外弁惑論)に記載されている漢方薬で、歴史ある処方の1つです。
また、処方名からも生脈散は気(エネルギー)・陰(潤い)を補充する働きがあります。
先ほども触れましたが
■ 人参は、気を補う補気薬の基本
■ 麦門冬は、陰を補う補陰薬の基本
■ 五味子…酸味(収れん作用)で陰の漏れを防ぎます。
気の働きには、固摂作用があり漏れ出ないようにする働きなどもあり、人参はこれにより過度の脱水を予防にも!!
また、単純に倦怠感などの疲れにも効果があるため夏バテ防止にもオススメでしょう。
陰の潤いの排出は、五味子で防ぎ、不足しがちの陰も麦門冬で補充する構成ですね。
ちなみに名前からも察するように、今にも途切れそうな脈を気・陰を補うことで生き返らせる意味があります。
そのため、夏バテといった夏だけでなく、1年中服用しても良いでしょう。
特に、高熱などの発熱後には、生脈散を!!
発熱すると、身体を冷やすために汗をいっぱいかきます。
すると、陰(水分)だけでなく、実は気も一緒に出ていくと考えられています。
発熱などの風邪の後に、体力が低下する理由がこれですね。
夏バテも同じく暑さにより、大量の汗が出てしまうことで同じような症状を引き起こします。
気の不足により、気虚になると疲労感・食欲不振・胃腸障害なども続いて生じます。
次に、補中益気湯についても話していきましょう。
気を補う代表的な漢方薬が、補中益気湯!!
補中益気湯の特色として、1番は身体を滋養する人参・黄耆・当帰などが配合されています。
また、気を上に持ち上げる働き升提作用(しょうていさよう)により、脱肛・内臓下垂などにも効果があります。
柴胡などの生薬を含むことで、疏泄作用を促すためストレスを流す働きもあるので、現代には欠かせない補気薬でしょう。
補中益気湯は10味の生薬で構成されており、人参・黄耆・蒼朮・陳皮・当帰・甘草が清暑益気湯と共通する生薬です。
補中益気湯との違いが、柴胡・升麻・大棗・生姜が含まれない代わりに、五味子・黄柏・麦門冬が配合されています。
補中益気湯の特徴である升提作用(しょうていさよう)に関与する升麻・ストレスを流す柴胡が含まれない代わりに、黄柏で清熱解毒・生脈散に配合される麦門冬・五味子により身体の蓄熱を除外しつつ陰(身体を冷やす力)を補う構成です。
つまり、夏バテや熱中症に特化させた処方である事が判ります。
清暑益気湯には、実は上記で紹介した9味の生薬に簡素化したもの・李東垣(りとうえん)による清暑益気湯である15味の生薬で構成されたものがありますが、9味の方が即効性であると言われております。
最近では、秋バテという言葉も耳にする事が多くなっています。
これは、夏で大量に消耗した陰が不足している事・夏バテから気が不足している事もあるので、この清暑益気湯が大事な漢方薬となっています。
また、秋からは乾燥が気になる季節でもあり、陰を補う生薬が含まれる清暑益気湯は、鼻粘膜や気管支などの保湿にも繋がるので、風邪予防にも良いでしょう。
まとめ
夏は、補気薬だけでなく補陰薬も欠かせません。
そんな時にこそ、清暑益気湯という漢方薬を試してみましょう。
また、口渇・ほてり・多汗などの熱中症で、身体に熱がこもっているなら、白虎加人参湯で急性の症状を緩和する方が良いでしょう。
清暑益気湯はあくまで、病気になる前の予防として服用すべき処方かと思います。
以上、参考になれば幸いです。